家族葬のイメージはさまざま

近年は、お亡くなりになる人の超高齢化、地域コミュニティの変化、葬儀に対する考え方の変化等を背景に、「家族葬にしたい」とご要望をいただくことがほとんどです。
家族葬という言葉が誕生したのは2000年ごろ。それまで内々で行う葬儀のことを「密葬」といわれていましたが、わかりやすくイメージしやすいこともあって、「家族葬」という言葉はわずか数年の間に広く浸透するようになりました。
家族葬の定義は、実はあいまい。
「近親者のみで行う葬儀」「近親者と親しい人が集まる葬儀」などをイメージされる方が多いと思います。
人数も家族3~4名程度から、親戚を含めて10~15名、友人・知人など30名程度、とさまざま。中には50名以上の家族葬もあります。
では、一般葬と家族葬の違いはなんでしょうか?
「一般葬」「家族葬」基本的な流れは同じ
一般葬と家族葬の違いですが、明確に「〇名以上は一般葬」と定義があるわけではありません。葬儀の流れも、
ご臨終→安置→(通夜)→葬儀・告別式→火葬(※地域によって火葬を先に行うケースもあり)
と一緒です。
ただ、家族葬の場合は限られた人に訃報を連絡する傾向にあり、一般に広く葬儀の日時・場所の告知は控えることがほとんどです。
家族の知り合い、同僚や上司、会社関係など、故人とは直接面識のない関係者などが参列しないため、家族葬は故人とゆっくりお別れできるメリットがあります。
社会的に地位のある人なら一般葬がおすすめ
故人が社会的地位のある方だったり、幅広い人脈を持っていた場合、どこからともなく死の知らせを聞いて参列者が殺到してしまうことも考えられます。
また、後から遺族宛にお悔みの連絡(電話やメール、SNSなど)が届くこともあるでしょう。
家族だけで送りたい、という気持ちとはうらはらに、想定通りにいかずかえって手間がかかったり、気疲れしてしまうことも考えられます。
故人が顔の広い方であるなら、一般葬として広く告知をしてお別れの場を設けた方が、葬儀では業者や親戚など周囲の助けがあるので喪主・遺族の負担が軽減されることもあります。
ご安置の期間の過ごし方が重要

家族葬でも一般葬でも、ご安置の期間をどのように過ごすか、という点がポイントになってきます。
故人とのお別れはセレモニーの最中だけではありません。ご安置の間、そばに付き添ったり、納棺やメイクに携わったり、故人と一緒に過ごす時間を設けることはできます。
また「一般葬は対応に追われてしまって、故人とゆっくりお別れができないのでは」と危惧される方もいますが、自分たちが知らない故人の別の顔を知ることができるのも一般葬の良いところです。
故人と深いかかわりをもっていた方だったにもかかわらず、遺族がその関係を知らなかったために訃報連絡が届かず「最後にお別れをしたかった」と悔いが残る人が出てくるかもしれません。「家族葬にする」と決めた場合は、このようなケースも想定して考えると良いでしょう。
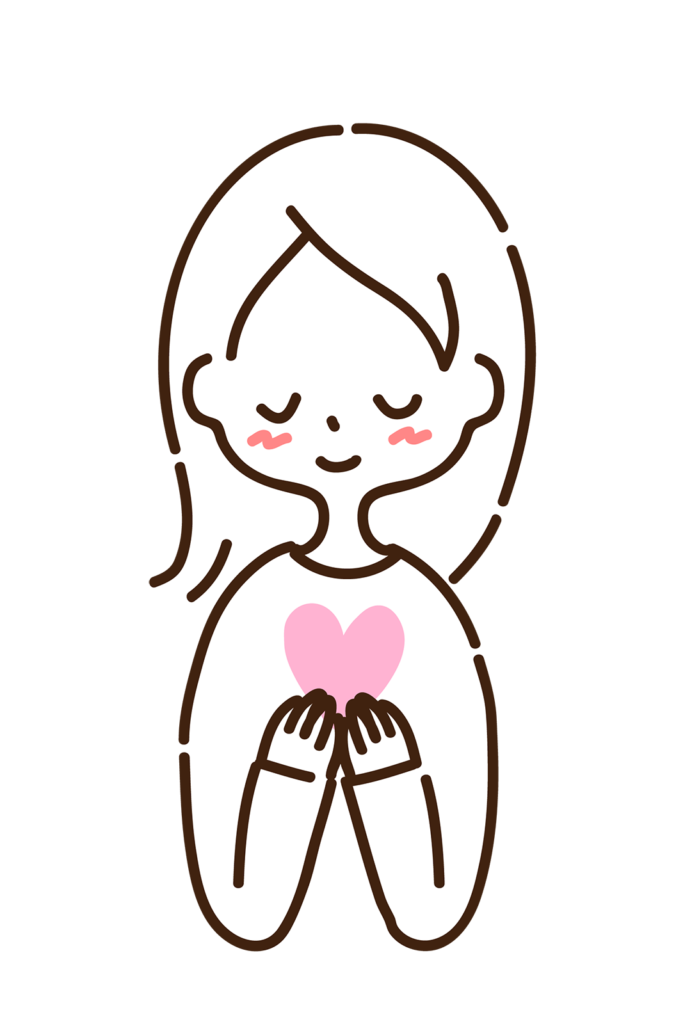
学研ココファンのお葬式「ここりえ」
吉川美津子
ここりえでは多くの家族葬の実績があります。自宅や公民館、寺院などでの家族葬のご相談も承ります。


 0120-323-800
0120-323-800 
 お急ぎの方へ
お急ぎの方へ

